| 好きなもの | 画・文:平澤 功 おもしろがりホーム |
| ▼ | ---- vol.1 ---- | |||||||||
| 好きなもの、お気に入りのことについて、思うところをメモってみました。 別に詳しいわけではありません。  |
090221 黒扇 090220 H.マンシーニ コーラス 090218 記憶の中だけの音楽 090214 フランク=シナトラ 090123 クァルテートEnCy 090112 赤毛のアン 081224 34丁目の奇跡 081202 マイルス=デイビス 081124 コルトー 081120 12人の怒れる男 081113 カラヤン |
|||||||||
| おすすめの出し物 | ||||||||||
| ※このコンテンツはブログの記事を再構成したものです。 | ||||||||||
| ページ先頭 | ▲ ▼ | |||||||
| 黒扇 | ||||||||
| 例えば、ルノワール展とかピカソ展といった企画展がやってくると、普段絵や彫刻なんて見向きもしない人でもこぞって美術館にやってくる。この半端でない集客効果を当て込んで、百貨店の催事場で展覧会が開かれることが多い。そして、大抵は、作品の数より圧倒的に多い人の数に辟易して、だんだん美術展に足を向けることが少なくなるのである。 それでは主催者側も困るので、メディアにも取り上げてもらって大々的な宣伝を繰り広げる。ところが、皮肉なことに話題になればなるほど大群集を見物するようなものなので、みんな招待券でもない限り、わざわざ見に行こうとは思わない。もっとも百貨店の場合はそれでも構わない。要するに、ついでの買い物さえしてもらえば初期の目的は達成したことになるからである。 しかし、そんなふうにして、美術に興味が失われていくのは残念なことだ。いや、美術鑑賞が好きな立場から言えば、人気がない方がゆっくり見られるので、複雑な気持ちなのだが。 ときどき、ふらっと美術館に行きたくなることがある。そんなときは、事前に調べて、企画展やら特別展示やらが「行われていない」美術館に出掛けるのである。と言うと、そんなところに行ってもつまらないだろうと思うかもしれない。 逆である。イベントも何にもないから、美術館の中は閑散そのもの。平日の午前中だと、広い展示室の中を私の足音だけが響いていることもある。 どんな美術館でも所蔵の美術品を公開してる常設展というものをやっている。これをバカにしてはいけない。それぞれの美術館に自慢の作品の一つや二つはあるもので、これが百貨店などの企画展に貸し出されたりするのだ。体力と気力をすり減らしてもチラッとしか見れない名品を、思う存分愉しむことができるのである。 東京駅の八重洲口を出て、ヤンマーのビルを右に見ながら大きな通りを真直ぐ進むと、中央通りの交差点に出る。その右向こう角がブリジストン本社ビルで、その奥にブリジストン美術館がある。私のお気に入りミュージアムの一つである。 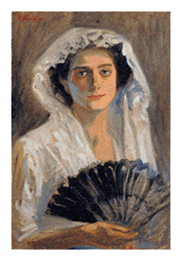 ここの所蔵品は有名なものばかりなので、半日かけてゆっくり見てもお釣りが来る。初めて来たのは、まだ学生だった。午後一杯まるまる時間を過ごしたのを覚えている。 ここの所蔵品は有名なものばかりなので、半日かけてゆっくり見てもお釣りが来る。初めて来たのは、まだ学生だった。午後一杯まるまる時間を過ごしたのを覚えている。
名画の数々をめぐって、あるフロアに来たときだ。その絵は他のすべての絵を消し去って私の目の中に飛び込んできた。絵の前でただため息をついている自分に気付いて、思わず周りを見渡した。誰もいなかった。顔が火照っているのが感じられた。 藤島武二画伯の「黒扇」。 この気品にあふれる美しさ、柔らかな光の中で静かに微笑む口元。優しく穏やかな視線をこちらに投げ掛けている。これは完璧にいかれたなと思った。フロアの中央に置かれた休憩用の椅子に腰を下ろし、それからの時間はただ「黒扇」を眺めるのみ。そう、午後一杯まるまるというのは、ほとんどこの絵の前で過ごした時間だった。 ときどき、ふらっと美術館に行きたくなることがある。それは、そこに行けば会えるお気に入りを、心行くまで堪能できるからだ。 ブリヂストン美術館の公式サイト http://www.bridgestone-museum.gr.jp/ |
||||||||
| (2009/02/21) | ||||||||
| ページ先頭 | ▲ ▼ | |||||||
| ヘンリー=マンシーニ・コーラス | ||||||||
| 私は紛れもないビートルズ世代である。すべてのアルバムに思い入れがある。ビリー=ジョエルも好きだし、スティービー=ワンダーも良いなあと思う。ところが、そんなビッグネームどころか、ほとんど表に出ることのない無名のアーティストの中に、忘れられない演奏があると、それはもう自分だけの宝物のように感じてしまうと言ったら少し大げさだろうか。 そういうアーティストの一つが、ヘンリー=マンシーニ・コーラス。 ヘンリー=マンシーニはだれでもよく知っている映画音楽の作曲家。彼自身のオーケストラによる演奏は、パーシー=フェイスとかビリー=ボーンなどと同じカテゴリーに入るから、要するに無難なムードミュージックといったところで、特段面白い音楽ではない。積極的に聞きたいと思ったわけでもない。実は、この前の記事「記憶の中だけの音楽」を追い求めた過程で出合った番外編なのである。 ところが、マンシーニの演奏に時々顔を出すモダンなコーラスが、なんとも言えない良い味を出しているのだ。と言っても、一般には全く知られておらず、私一人が勝手に思っているだけなので、専門家に言わせれば本当に大したことないのだろうとは思う。しかし、おそらくは実際に挿入歌として使われたであろうオリジナル演奏が、とても気分よく映画の名シーンを思い起こさせる。 オードリー=ヘプバーンの代表作の一つ、「ティファニーで朝食を」の挿入歌はアンディ=ウィリアムスが最もポピュラーだが、私はこのコーラスの演奏の方が好きだ。ヘプバーンは「音楽のない映画は燃料のない飛行機」と語り、マンシーニに尊敬を込めた感謝の手紙を贈ったと言われる。彼女の主演作品「シャレード」「いつも二人で」のテーマもこのコーラスのハーモニーを聞かせてくれる。 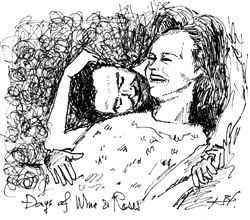 私の一番のお気に入りは「酒とバラの日々」。 私の一番のお気に入りは「酒とバラの日々」。ブレイク=エドワーズ監督、ジャック=レモン、リー=レミック主演の映画はアルコール中毒の物語。どこにでもある普通のラブコメディが酒によって壊れていく、そんなシリアスなストーリーの背景に流れる美しいメロディを、なんて素敵なハーモニーで聞かせてくれるんだろうと涙が出てきてしまう。「アラビアのロレンス」が席巻した1963年のアカデミー賞で、歌曲賞を引っさらったのは伊達ではない。 マンシーニのアルバムCDで聞くことができるので、特にコーラスとして追わなくても手に入れることはできる。オーケストラ演奏はほとんど聞かず、このコーラスだけを愉しんでいるというのは少々オタクっぽいかもしれないと、自分でも苦笑いなのである。 |
||||||||
| (2009/02/20) | ||||||||
| ページ先頭 | ▲ ▼ | |||||||
| 記憶の中だけの音楽 | ||||||||
 あんなによく聞いていたのに、いつの間にか耳にしなくなり、曲名も演奏者も知らないままメロディだけが記憶に残っているということがある。 あんなによく聞いていたのに、いつの間にか耳にしなくなり、曲名も演奏者も知らないままメロディだけが記憶に残っているということがある。 気になりだすと、どうしてももう一度聞きたくて、あれこれ調べずにはいられなくなってしまう。その挙句、レコードはすでに廃盤、手に入れることも聞くこともできないことを知って、悲しいやら切ないやら、なんとも表現し難い気持ちになる。 その最たるものがSo_in_Loveという曲。コール=ポーターのミュージカルKiss_Me_Kateの挿入歌で、結構たくさんの人が歌っているのだが、聞きたいのはこうしたカバーリリースではない。 昔、淀川長治さんが解説をしていた日曜洋画劇場という番組があった。エンディングの後、CMのバックにラフマニノフ風の印象的なピアノ協奏曲が流れていたのを覚えている人は少なくないだろう。あのSo_in_Loveが手に入らない。残念なことに、元になった録音すら残っていないという。これなど、そっくりそのままスコアを起こして再リリースすれば大ヒットすること請け合いと思うのだが。 実際にヒットした曲なら、オールディーズのCDの中に入っていることがあるので、それを手に入れれば良い。今はYouTubeなんて便利なサイトがあるので、そこで長年追い求めていた曲に出会うこともある。折々に聞いた流行曲の数々。例えば、スリードッグナイト、クリーデンス=クリアウォーター=リバイバル、ラスカルズなど、その名前を目にして、ああそうだ、これだこれだと懐かしく聞けるのは有難い。 しかし、お気に入りがそのB面だったりすると、これはYouTubeでもかなり難しい。みんなが良い曲だと思えるならともかく、たまたま耳にした個人的な好みのものは、当然ながらほとんど絶望的である。 これは、記憶をたぐり寄せて主旋律のみ記譜を試みたスコア。単に個人的な懐かしさがこみ上げてくるだけで、大した曲ではないのだが、曲名も演奏者もわからないまま、ずっとずっと探し続けている。 |
||||||||
 |
||||||||
| まだテレビが白黒の時代だったと思う。天気予報や行楽地案内のような番組のBGMに使われていた記憶がある。マントヴァーニやパーシーフェイスのようなストリングスを聞かせる演奏スタイルだったので、一時、軽音楽のCDを嫌になるほど聞きまくったが、結局わからず仕舞いで今に至っている。私の記憶の中だけで演奏が続いているのである。 |
||||||||
| (2009/02/18) | ||||||||
| ページ先頭 | ▲ ▼ | |||||||
| フランク=シナトラ | ||||||||
| 中学生だった。英語を学び始めた最初のテストでたまたま満点を取っってしまい、何を勘違いしたか、優等生気分で洋楽ファンの真似事をしていた。優等生なので、どんなに流行していても大人が眉をひそめる長髪のビートルズはご法度。代わりによく聞いたのはアンディ=ウィリアムス。テンポの緩い映画音楽やバラードが多いので、歌詞が聞き取りやすく、英語の先生もお薦めのシンガーだった。 シナトラを知ったのもほとんど同時期だったが、アンディ=ウィリアムスのソフトで伸びのある声に慣れてしまった耳には、どうも声量不足でクセがある。最初に聞いたのは「マイファニーヴァレンタイン」。ところが、これが妙に耳に残る。意味もわからずに歌詞が頭の中を駆け巡る。大人の香りというか、悪ガキの理解を超えた不思議な雰囲気。 マイルス=デイビスの稿でも述べたように、ジャズに目覚めるのはずぅっと後のこと。おまけに、いい気になって英語の勉強をおざなりにしていたせいで、成績はどんどん下がる一方。こうなると、聞く音楽もめちゃくちゃで、加山雄三やらグループサウンズやら吉田拓郎やら、要するに流行歌を追うだけのミーちゃんハーちゃんに落ちぶれてしまっていた。  古いレコードの整理をしていた時だ。「マイファニーヴァレンタイン」が再び目の前に現れる。ポンコツのプレーヤーにかけてみると、あの大人の香りがよみがえってきた。たとえて言うなら、子供の頃には食べられなかったワサビやらニガウリやらサンマの内臓やらが、大人になってやたらに美味く感じるようなもの。あるいは煙草の臭い、酒の味。一度とりこになると止められないというやつだ。 古いレコードの整理をしていた時だ。「マイファニーヴァレンタイン」が再び目の前に現れる。ポンコツのプレーヤーにかけてみると、あの大人の香りがよみがえってきた。たとえて言うなら、子供の頃には食べられなかったワサビやらニガウリやらサンマの内臓やらが、大人になってやたらに美味く感じるようなもの。あるいは煙草の臭い、酒の味。一度とりこになると止められないというやつだ。
マイクをスタンドから外して歌った最初のシンガーであり、ボビーソクサー(女学生)のアイドルとか、シナトラ一家とか、華やかな面がやたらに強調され、ハリウッド映画にも数多く出演しているが、役者としてはちょっと首を傾げる。やはり、ジャズシンガーとしての魅力が大きい。 「マイファニーヴァレンタイン」は多くのシンガーがレパートリーに入れているが、やっぱりシナトラが秀逸だと思う。この曲が収められているアルバム「ソングズフォーヤングラヴァーズ」と、同じく大ヒットしたアルバム「スウィングイージー」が1枚のCDにカップリングされている。いずれも聞き応えのある、ご機嫌なラインナップだ。特に「手紙でも書こうよ」は、シナトラの巧さを存分に味わえる私のお気に入りの1曲。 その後、マフィアとの係わりやら数々のスキャンダルでパッとしない時期がしばらく続き、よくご存知の「マイウェイ」で再び脚光を浴びることになる。ただ、「夜のストレンジャー」や「ニューヨークニューヨーク」といった彼自身のヒット曲はともかくとして、素人受けする無難なスタンダードナンバーはあんまり面白くない。「ムーンリヴァー」なんて最悪。これはやっぱりアンディ=ウィリアムスのようなクソ真面目な歌い方の方が良い。 よほどのジャズ好きでないと知らないようなB級ナンバーの方が、私は聞き飽きない。 |
||||||||
| (2009/02/14) | ||||||||
| ページ先頭 | ▲ ▼ | |||||||
| クァルテート エン シー | ||||||||
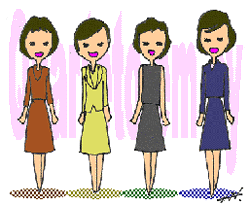 クァルテートエンシーを知ったのは、比較的最近のことである。したがって、浅薄なウンチクをひけらかすのは気が引けることこの上なく、古いファンの方にはどうか目をつぶっていていただきたい。 クァルテートエンシーを知ったのは、比較的最近のことである。したがって、浅薄なウンチクをひけらかすのは気が引けることこの上なく、古いファンの方にはどうか目をつぶっていていただきたい。
クァルテートエンシーは、ボサノヴァが世界的に大ヒットした60年代にデビューしたブラジルの女性コーラスグループ。サルヴァドール生まれの4人姉妹、シーヴァ、シベーリ、シナーラ、シレーネの名前の頭文字をとって、クァルテートエンシー(Quarteto_em_Cy)と名付けられた。その後メンバーの入れ替えもあったが、今も現役で活躍している様子をYouTubeで見ることができる。ただし、さすがにおばあちゃんになって衰えは隠せないので、この映像をもって判断をして欲しくない。 私が初めて聞いたのは、数年前渋谷のHMVでジャズのCDを物色しにフロアに入った時だ。フロアのプロモーション用に流れていた彼女らの歌声に一瞬で心を奪われてしまった。ボサノヴァの詩人と言われるヴィニシウス=モライスの作品を集めた「ヴィニシウスエンシー」というCDで、資料を見ると1993年リリースだが国内では2001年4月とあるので、おそらくその発売に偶然巡りあわせたのだろう。 ボサノヴァと言えば、あの独特のリズムに乗って、かすれ声で独り言を呟くようなジョアン=ジルベルトの弾き語りが思い出される。同じブラジルの代表的な音楽であるサンバの情熱的な派手さとは正反対の、鼻歌のような弛緩した穏やかさが心地良い。クァルテートエンシーの原点もボサノヴァであるが、その音楽は、呟きの中のかすれが静かにろ過されたように澄んだハーモニーとなって、女性コーラスならではの美しい音の世界を創り出している。 彼女らを知るまで、私にとって最も魅力的な女声ハーモニーは、フィガロの結婚でスザンナと伯爵夫人が歌う「手紙の二重唱」だった。今でも、このデュエットの美しさにはため息が出てしまうばかりだが、さすがに本格的なオペラの挿入歌なので、何度も繰り返して聞けるような、あるいは聞き流すことができるような軽さはない。 クァルテートエンシーの魅力は、姉妹というよく似ている声質が生み出す、どこか懐かしさのある自然なハーモニーだ。ソロからデュエット、ユニゾンからハーモニーと繰り広げられる巧みなコーラスの綾が、軽やかに動きまわる音の広がりとなって、聞いている者をホッとさせる。これに近い声質と巧さを持っていると思うのはかつてのザピーナツなのだが、不幸なことに彼女らは日本の歌謡曲というローカルな文化の中で異彩を放っていたに過ぎない。ボサノヴァは今やグローバルなミュージックスタイルとしてジャズやポップスの中に定着している。その随一の女性コーラスグループとして、クァルテートエンシーは世界中の音楽ファンに知られているのである。 日本にももっと多くのファンがいておかしくないと思うのだが、CDもよほど大きな店に行かないとなかなか手に入りづらいのが残念でならない。入手できるのなら、できるだけ若い頃のオリジナルメンバーの録音を聞いてみて欲しい。いち押しである。 |
||||||||
| (2009/01/23) | ||||||||
| ページ先頭 | ▲ ▼ | |||||||
| 赤毛のアン | ||||||||
| Matthew! Matthew, what is it? マシュー!マシュー、どうしたの? |
||||||||
| 抱き起こされたマシューがアンの手を握る。 | ||||||||
| I'm all right. 大丈夫だ。 |
||||||||
| Please, Matthew. You need help. I've got to get a doctor. だめよ、マシュー。あなたには助けが要るわ。お医者さんを呼ばなければ。 |
||||||||
| I worked hard all my life...I rather...drop in the harness...I got old, Anne...I got old. I never noticed... わしは懸命に働いてきた・・・もうここで死んでもいい・・・わしは年老いた、アン・・・こんなに年老いていたとはな・・・ |
||||||||
| If I'd been the boy you sent for, I could have spared you in so many ways. あたしが男の子だったら、代わりに仕事をたくさんできたのに。 |
||||||||
| I never wanted a boy...I only wanted you from the first day. 男の子が欲しいなんて思ったことはない・・・最初からおまえだけが欲しかったよ。 |
||||||||
| アンの頬を涙が伝う。 | ||||||||
| Don't ever change...I love my little girl...I'm so proud of you. いつまでもそのままでいておくれ・・・愛しているよ・・・おまえはわしの誇りだ。 |
||||||||
| Matthew...Don't... マシュー・・・死なないで・・・ |
||||||||
 息を引き取るマシューをアンがやさしく抱く。ここで、カメラが引いていき、グリーンゲイブルズの牧場風景がスクリーン全体に広がる。このなーんと美しいこと! 息を引き取るマシューをアンがやさしく抱く。ここで、カメラが引いていき、グリーンゲイブルズの牧場風景がスクリーン全体に広がる。このなーんと美しいこと!カナダの作家モンゴメリの名作「赤毛のアン」について、改めて説明する必要はあるまい。世界中から愛される少女の物語で、繰り返し舞台劇に取り上げられたり、ドラマ化が行われている。1985年にケヴィン=サリヴァン監督、ミーガン=フォローズ主演で完全映画化され、大ヒットした。 ミーガン=フォローズの髪はブロンドに近く、赤毛というには少し抵抗があるが、多感で前向きで活発な主人公を魅力的に演じている。「歓びの白い道」を行く馬車、マリラと手をつないで歩く田舎道、「輝く水の湖」に掛かる橋など、上の場面以外にも息を飲むような美しい光景の中で、なんて可愛らしい女の子なんだろうと思わずにはいられない。 でも、私が最も気に入っている場面は、ダイアナの妹が喉頭炎になった時にアンが子守りのメリー=ジョーに言った言葉。 |
||||||||
| I don't hurt your feelings, but you might have thought of that before if
you had any imagination. あなたの気を悪くさせるつもりはないの。でも、ちょっと想像力があれば、もっと前に気付いたはずだわ。 |
||||||||
| こんな映画、企業の経営者、管理者が真面目な顔をして見ることもなかろうが、これはまさに危機管理の心得、問題発見の極意のようなものだ。どこぞの大臣さんにも聞かせたいくらいだ。全く、舌を巻くほど、このお嬢さんには感心させられる。 アンの寝ずの看病の甲斐あって子供の容体は落ち着き、後を任せて帰る雪道。橇の上でマシューの肩に顔を乗せて眠るアンの愛らしさ! 想像力。あなたは必要な時にちゃんと働かせていますか? |
||||||||
| (2009/01/12) | ||||||||
| ページ先頭 | ▲ ▼ | |||||||
| 34丁目の奇跡 | ||||||||
 AFNをつけると、メリークリスマスよりもハッピーホリデイズというフレーズの方が多く聞こえてくる。アメリカは多民族国家なので、最近はキリスト教以外の人もいるのを意識して使うのだそうだ。 AFNをつけると、メリークリスマスよりもハッピーホリデイズというフレーズの方が多く聞こえてくる。アメリカは多民族国家なので、最近はキリスト教以外の人もいるのを意識して使うのだそうだ。私の家も門徒で本来なら全く関わりがないけれども、今日はクリスマスイヴなので、この映画を取り上げてみる。 豊かなアメリカの家庭に育ち、夢のない冷めた目で社会を見つめる少女の前に現れた一人の老人。自らサンタクロースと称する彼を、現代社会は当然のように変人扱いするが、不思議なことに、彼の周りで次々と願い事が適い、人々が幸せになっていく。ところが、この評判を妬む力によって罠にはめられ、絶体絶命の窮地に陥ってしまうというストーリー。続きはみんなでゆっくり愉しむのが良かろう。 この時期、子供の頃はサンタクロースを信じていたのに、実は自分の親だと気付いて・・・なんていう話題で盛り上がる。いつまでも夢を抱いていたいという願望と、いずれは現実に目覚めなければならない必然との葛藤は、この話に限らず、人が成長する過程で常に悩まされる問題である。心地良いクリスマスソングに乗せられて、単なる夢物語と片付けても構わないが、この映画の主題もそんなところに置かれているように思う。 アメリカという国は、社会保障や経済格差、犯罪発生などを見ると、決して人に優しい国とは思えない。しかし、映画の最後に登場するあるアイテムが、この国の懐の深さを物語っている。政教分離が近代政治の鉄則とはいえ、実は価値観の根底にある信仰が、荒廃する人の心を救っている国なのだ。 これでも私は理数系の人間なので、実体の見えない神仏よりも実証を旨とする科学を信奉しているが、この映画を見ると、いつも信仰の大切さを思ってしまう。ほとんどの人は、神仏など特に気に留めなくても、ごく普通にささやかな幸福を味わいながら暮らしている。しかし、人は決して一人で生きていくことはできない。助け合っているとしても、絶望という縁に立たされることは誰にでもある。そんなときは、どんな宗教でも良い、やはり神仏に頼るしかないではないか。 信仰のある人は強い。自分で精一杯努力し、人事を尽くして天命を待つ。天命?・・・言葉で言うのは簡単だが、本当に神仏を信じていなければウソになる。 クリスマスの意味も知らず、ただ愉しいパーティをやって高価な贈り物がもらえる日という認識。大切なのは信仰よりお金というのが今のこの国の一般的価値観。信仰を商売のように捉え、やたら信者を増やすことしか考えない宗教もある。本物の信仰がないから、景気の良い時は自分のことしか考えず、不景気になると他人を恨むようになる。 今日は聖夜。せめて、祝おう、ささやかなクリスマスを。クリスチャンはもちろん、そうでない人もみんな幸福ということについて考えてみよう。お金では買えない夢について語り合おう。そして、夢を語る自分の存在を感謝しよう。両親に、ご先祖様に、神様あるいは仏様に。そんなクリスマスの過ごし方があっても良いのではないかな。 信じてごらん。そんな夜にサンタクロースは来るよ、きっと。 |
||||||||
| (2008/12/24) | ||||||||
| ページ先頭 | ▲ ▼ | |||||||
| マイルス=デイビス | ||||||||
| まだ植木等に狂っていた悪ガキ時代のことである。なぜそういう羽目になったのかよく覚えていないのだが、ジャズとはこういうものだと言われて、私が一番最初に聞いたのがオーネット=コールマンだった。当然のことで、ジャズとは格調高いクラシックと対極にある目茶苦茶な雑音であると刷り込まれてしまった。その後、ルイ=アームストロングやベニー=グッドマンなど古いスタイルのジャズを耳にしても、それらはポップスや軽音楽の一種だと思っていた。 ラジオの深夜放送が流行っていた。十代の若者たちが慢性的に寝不足なのは今も昔も変らない。ナッチャコやキンキンケンケンなんていうのは別格の人気パーソナリティーだったが、私がよく聞いたのは糸居五郎さんのオールナイトニッポン。テーマミュージックにジャズを流す垢抜けた雰囲気が好きだった。ところが、このときに至ってもまだ、それがジャズであるという認識をしていな  かった。 かった。あるとき、妙に耳に残る曲が流れてきた。糸居さんのあの独特な口調で、それがマイルス=デイビスのマイルストーンズという曲であることを知って、初めてこれがジャズなのかと目が覚めた。普通マイルス=デイビスのベストアルバムと言えばカインドオブブルーだが、私がマイルストーンズの方が好きだと言うと友達が笑うのである。 かといって、それをきっかけにジャズに傾倒していったわけではない。相変わらず気軽に聞き流せる音楽と思っていたし、今でも私にとっては生活の中で自然にムードを盛り上げてくれる音楽がジャズ。気持ちの良い音楽。それ以上の理屈を語る気はない。 一口にジャズと言っても色々なスタイルがあるわけだが、評論家の植草甚一さんの解説書を読むと、新しいスタイルの確立には必ずマイルス=デイビスが名を連ねていて、この人がジャズの歴史そのものであることがよくわかる。実際、ジョン=コルトレーン、ビル=エバンス、アート=ブレーキーなど、共演者のビッグネームを見るだけで胸がわくわくしてくる。やっぱりスティーミンとかクッキン、ワーキンといった50年代のアルバムが好きだ。 ところで、マイルス=デイビスは上述のオーネット=コールマンを批判したと言う。それで気付いたことがある。オーネット=コールマンと言えばフリージャズ。しかし、これは(少なくとも私は)構えないと聞くことができない。そこに感じられるのは混沌、不安、恐怖、不条理といったもので、決して気持ちの良いものではない。しかし、間違いなくある精神世界を表現しているという点でこれも音楽なのだろうと、そう納得できたのはマイルス=デイビスの気持ちの良いジャズのおかげなのだ。 |
||||||||
| (2008/12/02) | ||||||||
| ページ先頭 | ▲ ▼ | |||||||
| コルトー | ||||||||
 今はクラシック音楽もポピュラーに聞かれるようになり、のだめカンタービレみたいなドラマもヒットして、裾野もかなり広がっているようだ。趣味でピアノをたしなむ人が珍しくなくなったし、素人でもショパンのエチュードやポロネーズのようなかなり難しい曲を弾いてしまう人もいる。 今はクラシック音楽もポピュラーに聞かれるようになり、のだめカンタービレみたいなドラマもヒットして、裾野もかなり広がっているようだ。趣味でピアノをたしなむ人が珍しくなくなったし、素人でもショパンのエチュードやポロネーズのようなかなり難しい曲を弾いてしまう人もいる。しかし、好き嫌いを云々する以前に、音大の学生か余程のオタクでもない限り、コルトーなんて知らないと言う人の方が多いかもしれない。 かつて、ショパンと言えばコルトーであった。カザルス(チェロ)、ティボー(ヴァイオリン)といった名前すら知らないと言われれば、もはや何をか言わんやであるが、こういった名演奏家と同時代の偉大なピアニストの一人である。 当然、今出ているCDもその時代の演奏で、古いSP盤をダビングしたものを聞くことになる。最新の録音技術で透き通った音色が当たり前になっている人には、ノイズの混じったモノラル録音自体が聞くに耐えないだろう。今はどんなにヘタクソな演奏でも、録音技術で修正できてしまう時代である。そういう音楽に慣れてしまって、演奏の底に流れる音楽性に触れようとしない人には、残念ながらコルトーの音楽を愉しむことはできないと思う。 コルトーを知っている人でも好きになれないと言う人は多い。その理由を聞くと、感情の起伏が激しすぎて、曲目によってはミスタッチも目立つ演奏についていけないと言う。しかし、私など、それがまた逆にコルトーの魅力と感じてしまう。楽譜と演奏とを比較してみるといい。正真正銘楽譜どおりの演奏。しかし、それぞれの曲が一篇の詩を朗読しているかのような演奏は、強い感情の注入と同時に、冷静かつ緻密に計算された解釈がなされていると思わずにいられない。技術ではない。音楽という芸術が姿を変えて、壮大なオペラが展開される異次元空間の中に我々をいざなっているのだ。 楽譜は標準の世界である。実際の演奏というのは、この標準を中心値にして釣鐘状に広がるバラツキの中で、様々なヴァリエーションとなって聴く側にもたらされる。標準の音楽は誰にでも作れるが、つまらない。ところが、許容されるバラツキの限界ギリギリのところで創造される音楽は、間違いなく聴く者の心を揺さ振り、賞賛あるいは非難の的となる。それが芸術である。 私がコルトーを知ったのは高校時代。織田久男先生という音楽の先生が自ら演奏されていたショパンのバラードに魅せられて、その音楽の原型をうかがったのがきっかけであった。音楽ではなく美術を選択していた私がこの素晴らしい先生と係わることになるのは、また話せば長いエピソードがあるわけで、それについては別の機会に語ることもあるだろう。 とまれ、織田先生によってコルトーを知り、音楽の深さ、面白さを知ることができたのは大きな幸運だったと強く思うのである。 |
||||||||
| (2008/11/24) | ||||||||
| ページ先頭 | ▲ ▼ | |||||||
| 12人の怒れる男 | ||||||||
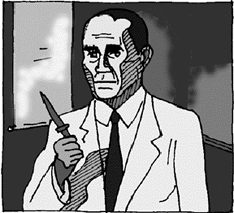 一人の若者の殺人罪の評決をめぐって、閉ざされた部屋の中で議論を繰り広げる12人の陪審員の物語。互いに見ず知らずの登場人物それぞれが持つ信条、嗜好、偏見、生活背景などが絡み合いながら、一つの結論を導き出すまでの葛藤を淡々と描いていく。 一人の若者の殺人罪の評決をめぐって、閉ざされた部屋の中で議論を繰り広げる12人の陪審員の物語。互いに見ず知らずの登場人物それぞれが持つ信条、嗜好、偏見、生活背景などが絡み合いながら、一つの結論を導き出すまでの葛藤を淡々と描いていく。もともとはレジナルド=ローズという脚本家が1955年にTVドラマ用の戯曲として書かれたもので、57年にシドニー=ルーメット監督、ヘンリー=フォンダ主演で映画化された。 傍聴する以外に一般民間人が裁判に関わるということがなかった日本では、物語の状況自体に実感がわかないかもしれない。来年から始まる裁判員制度を控えて参考になるだろうが、アメリカの陪審制度とはいくつかの点で大きな違いがあるので、そっくりそのまま制度のシミュレーションとして捉えるのもムリがあると思う。 しかし、様々な価値観の人間が、手元にあるだけの証拠、証言をもとにして、どこまで事実を証明できるか、可能な限りの議論を繰り返す展開は見応えのある人間ドラマである。 真夏の暑苦しい個室という設定がそのままこれから始まる激論を予感させ、さらに話合いが打開点を見出せないまま停滞すると、外が夕立となって画面全体が暗くなり、重苦しさをいっそう際立たせる。白黒画面がその明暗を強調しているので、非常に効果的に場の雰囲気を印象付けている。 それが、あるきっかけで急展開に評決へとつながり、狭い個室から出て雨上りの戸外が広がるラストシーンがすがすがしい。気分よく見終わることができる演出が見事だ。 制作当時の社会背景が反映していて、女性や黒人が全く出てこない。もちろん、CGを駆使した特撮もなければ、派手なアクションやロマンスがあるわけでもないので、今どきの映画ファンには退屈だろうと思う。言わば、ただの舞台劇をスクリーンに映しただけ。しかし、裏返せば演じている役者に確かな技量がなければ決して作れない映画であり、実際、陪審員を演じた12人はいずれも玄人好みの古き名優ばかりだ。 笑われるだろうが、おそらく100は優に超える回数を見ていると思う。未だに見飽きることがない。この映画のおかげで英語耳を作ることができたと言ってもよい。 事実に対する真摯な姿勢、生命を第一に考える価値観、他人を思いやる人間性、自ら考え自らの意見を持つことの大切さ、発言し行動する勇気、そういったものを見るたびに教えられる。私にとっては随一の映画である。 |
||||||||
| (2008/11/20) | ||||||||
| ページ先頭 | ▲ | |||||||
| カラヤン | ||||||||
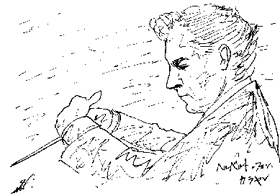 生まれて初めて買ったクラシック音楽のレコードは、エドワード=シュトラウス2世指揮のウィンナワルツ集だった。まだ小学生だったと思う。その時、レコード店のいたる所にカラヤンのチラシが貼ってあり、名前だけは確かに記憶に刻んだが、大した興味も持たなかった。実際問題として、お上品なクラシックなどより、植木等のスーダラ節の方が断然お気に入りの悪ガキだったのだから、当然と言えば当然の話である。 生まれて初めて買ったクラシック音楽のレコードは、エドワード=シュトラウス2世指揮のウィンナワルツ集だった。まだ小学生だったと思う。その時、レコード店のいたる所にカラヤンのチラシが貼ってあり、名前だけは確かに記憶に刻んだが、大した興味も持たなかった。実際問題として、お上品なクラシックなどより、植木等のスーダラ節の方が断然お気に入りの悪ガキだったのだから、当然と言えば当然の話である。そのカラヤンを再び目にするのは、高校生の時に京橋のフィルムライブラリー(現在の国立近代美術館フィルムセンター)で、ベルリンフィルの映画が上映されていたのを見たときだ。クソ悪ガキも生意気に青春を語るようになっていて、一丁前にクラシックも聞けるような情操が身についていたと思って欲しい。 小さな会場内にベートーベンやブラームスが流れるのに同期して、これまた小さなスクリーンにモノクロの演奏風景が映し出されるわけであるが、その中に悠然と立ってタクトを振るカラヤンのカッコよさ。音楽は聴くものという固定概念が木っ端微塵に砕かれた瞬間だった。 指揮法については何も知らない。ただ、だれもがやるようなリズムを刻むだけの単純なタクトの振り方でないことは一目瞭然である。腰から下は根っこが生えたかのようにどっしりと動かず、その上で、まるで魔法使いが呪文を切るがごとく腕を回転させると、目の前に大きな異次元空間が広がって見えた。かと思えば、肩をわずかに傾ける以外は何の動きもないのに、鳥肌が立つような深いクレッシェンドが起きるのである。こういう立っているだけで見せる指揮者というのは、後にも先にもカラヤンしか知らない。 カラヤンは、若いときから映像に非常に興味を持っていて。盛んに自らのオーケストラ演奏を記録に残した指揮者だった。あの端正な顔立ちと相まって、記録映画と言うよりも劇映画と言って良いくらいのパフォーマンスである。何度繰り返して見ても飽きが来ない。 ベートーベンの交響曲第7番と、幼さの残るキーシンのピアノによるチャイコフスキーの協奏曲第1番が特に好きだ。 |
||||||||
| (2008/11/13) | ||||||||
| Copyright (C) omoshirogari. All Rights Reserved. |